【解説】遺産の全容を調査する方法
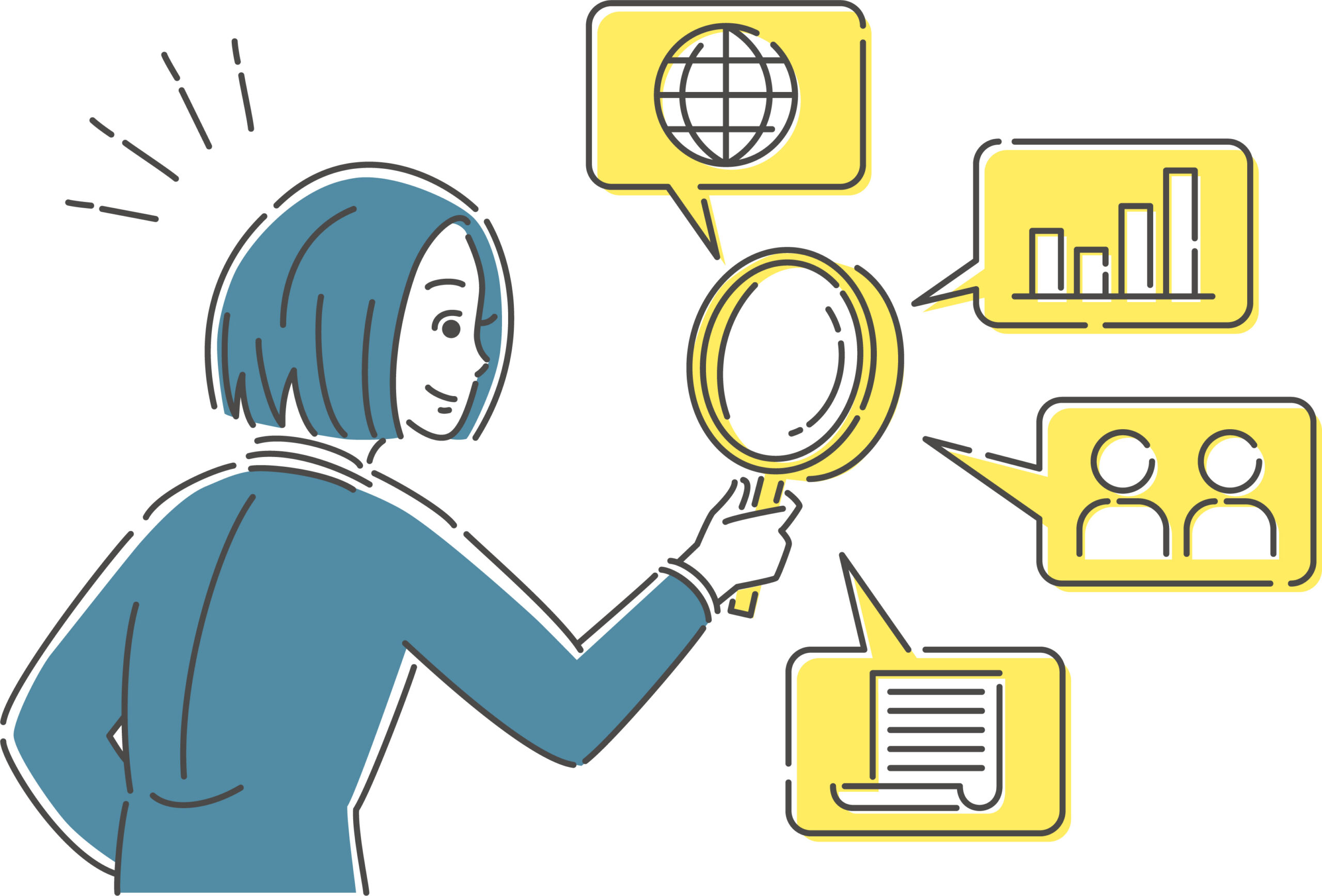
このページをご覧の方は、相続人になったけれども遺産の全容が分からない、遺産の全容を知りたいけれども他の相続人とトラブルがあり教えてもらえない(あるいは関係が疎遠であり尋ねづらい)、といったお立場の方が多いと思います。
他の相続人の助けを得ずに遺産を調査する方法について、各財産ごとに説明します。
不動産
被相続人の自宅の中で重要書類が保管されている場所や、銀行の貸金庫の所在を確認できるようであれば、まずはそこを確認します。権利証や固定資産税課税明細書など不動産に関する書類が出てくる可能性があります。
被相続人の不動産の存否や所在地が全く分からない状態で調査をする場合、市区町村から固定資産の「名寄帳」(なよせちょう)を取り寄せる方法があります。名寄帳は、課税の対象となっている固定資産(土地・家屋)を所有者ごとに役所が一覧表にまとめた資料で、地番や家屋番号といった不動産を特定する重要な情報が掲載されています。
名寄帳は、市区町村ごとに作成されるものです。複数の市区町村に不動産を保有している可能性があるのであれば、各市区町村に対して名寄せ帳の発行を請求した方が良いです。
名寄帳は過去5年分程度(市区町村により差があります)を取得することができます。過去の名寄帳を調べることで、既に被相続人の名義でなくなってしまった不動産が判明することがあります。
相続人の立場にあれば、(共同相続人全員一緒でなくとも)単独で役所に対して名寄帳の発行を請求できます。
なお、近時、「登記簿図書館」というウェブサービスを利用すると、インターネット上で不動産情報の名寄せをすることができるようになりました。弁護士が当該サービスを利用することも増えてきていますのでご参考ください。
名寄帳等により土地建物の存在が判明した場合、登記情報を調査することで、最新の権利関係(所有名義、担保権付着の有無等)を調べることができます。
登記情報は、一般に公開されている情報なので、相続人はもちろん他人であっても調べることが可能です。登記情報は全国どこの法務局からでも取り寄せることができます。
また、登記簿謄本と同等の情報を、「民事法務協会」が運営するインターネット上の登記情報提供サービスを利用して即時に取得することができます。費用は1件当たり300円程度ですので、非常に簡単かつ迅速です。
不動産の権利関係が分かったら、不動産業者の査定を取得するなどして、不動産のおおよその実勢価格を調べます。
預貯金
被相続人の通帳を確認できるのであれば、まずは通帳の中身を確認します。日付が古い場合は通帳を記帳することで最新の情報がわかります。
通帳が見当たらない場合は、財布の中のキャッシュカード、カレンダーやボールペンといった金融機関からもらえるノベルティ等を探してみます。もしパソコンやスマートフォンの中身を確認できるのであれば、取引のある金融機関のアプリやブックマークがあるかもしれません。
被相続人が口座を持っている金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農協など)が分かれば、相続人としての資格で、残高証明書及び預金(貯金)取引の明細を取り寄せることができます。具体的な支店名が分からない場合でも、全店検索をしてもらえる金融機関があります。
被相続人が取引していた銀行等が分からない場合、残念ながら、全ての金融機関を網羅的に調査する方法はありません。被相続人が取引をしていた可能性がありそうな銀行等に対して、個別に、照会をすることになります。
高齢の方は郵便貯金を保有していることが多いですので、ゆうちょ銀行への照会は必須と考えた方が良いでしょう。若年青年の方は、通帳が発行されないネット銀行の口座をお持ちの方も多いです。
被相続人がどの銀行等と取引をしていたのか全く心当たりがない場合には、googlemapなどインターネット上のマップを利用して、被相続人の居住地近くに存在する金融機関を調べ、個別に照会をしていくことになります。
口座の存在がヒットすると、相続開始時の残高だけでなく、過去10年程度の取引明細書を取り寄せることができます(金融機関によってはそれより古い情報を取り寄せることができる場合もあります)。そこで、残高証明書だけでなく、取引明細書も取り寄せ、どのような入金、出金があったのかをチェックすることをお勧めします。
取引明細をチェックすることにより、他の預貯金口座、証券口座、保険契約など他の財産の存在が発覚することもあります。
また、被相続人の生前に多額の金銭が預貯金口座から引き出され、特定の相続人が着服している事実や、特定の相続人に高額な生前贈与がなされている事実が発覚することもあります。
なお、相続人であれば、普通は、一人であっても金融機関に対して預金取引明細、残高証明書の発行を依頼することが可能です。ただし、すべての遺産、あるいは当該預貯金を、特定の相続人へ相続させる旨の遺言書が存在する場合、預金情報の開示を拒否する金融機関もあります。このような場合には、弁護士法23条に基づく「弁護士会照会」という弁護士のみが利用できる手段を講じることにより、情報を取得できる場合もあります。
有価証券(上場株式等)
被相続人と付き合いがあった証券会社、信託銀行などの金融機関名に心当たりがある場合は、当該金融機関に対して個別に、残高証明書や取引明細の発行を依頼します。付き合いの有無は、預貯金口座と同様に、自宅の重要書類の保管場所、貸金庫、ノベルティ、パソコンやスマホのアプリ等が手がかりにもなります。
被相続人が取引していた証券会社等が分からない場合、証券保管振替機構(通称:ほふり)に対し、登録済加入者情報の開示請求を行います。これにより、被相続人がどの証券会社等に口座を開設しているのかを調べることができます。そこから判明した証券会社等に対し個別に、残高証明書や取引明細の発行を依頼します。
負債
被相続人が、友人や親戚といった個人に対して負債については、心当たりのある個人に問い合わせて確認するしかありません。
他方、金融機関や業者に対して債務を負っている場合、業者名が分かっていれば相続人として個別に照会することで、債務の有無、残高等の詳細について回答が得られます。
どこの金融機関や業者に対して負債があるのか分からない場合には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)という信用情報機構に照会することで、信用情報機関に登録されている債務の詳細を確認することができます。
相続問題を専門的に取り扱う弁護士に遺産調査を依頼するメリット
相続問題を専門的に取り扱う弁護士は、遺産調査を日常的な業務として取り扱っています。過去の実績によるノウハウを活かして、何を優先的に調査すべきなのかをスピーディに判断し、手続きをスムーズに進めることが可能です。
また、発見できた財産の価値、評価額を見積もることについても、日常的な業務として取り扱っています。遺産の全容が分かった後に、遺産全体の評価額についてもスムーズに調査することが可能です。
特に、相続を放棄する否かを決断する必要がある場合は、「3か月」という短期間のうちに「相続放棄」の申述をするか否かを判断しなければなりません。そのための書類の準備も必要です。
遺産調査は、できる限り、相続問題を専門的に取り扱う弁護士に依頼することをおすすめします。