【解説】相続放棄
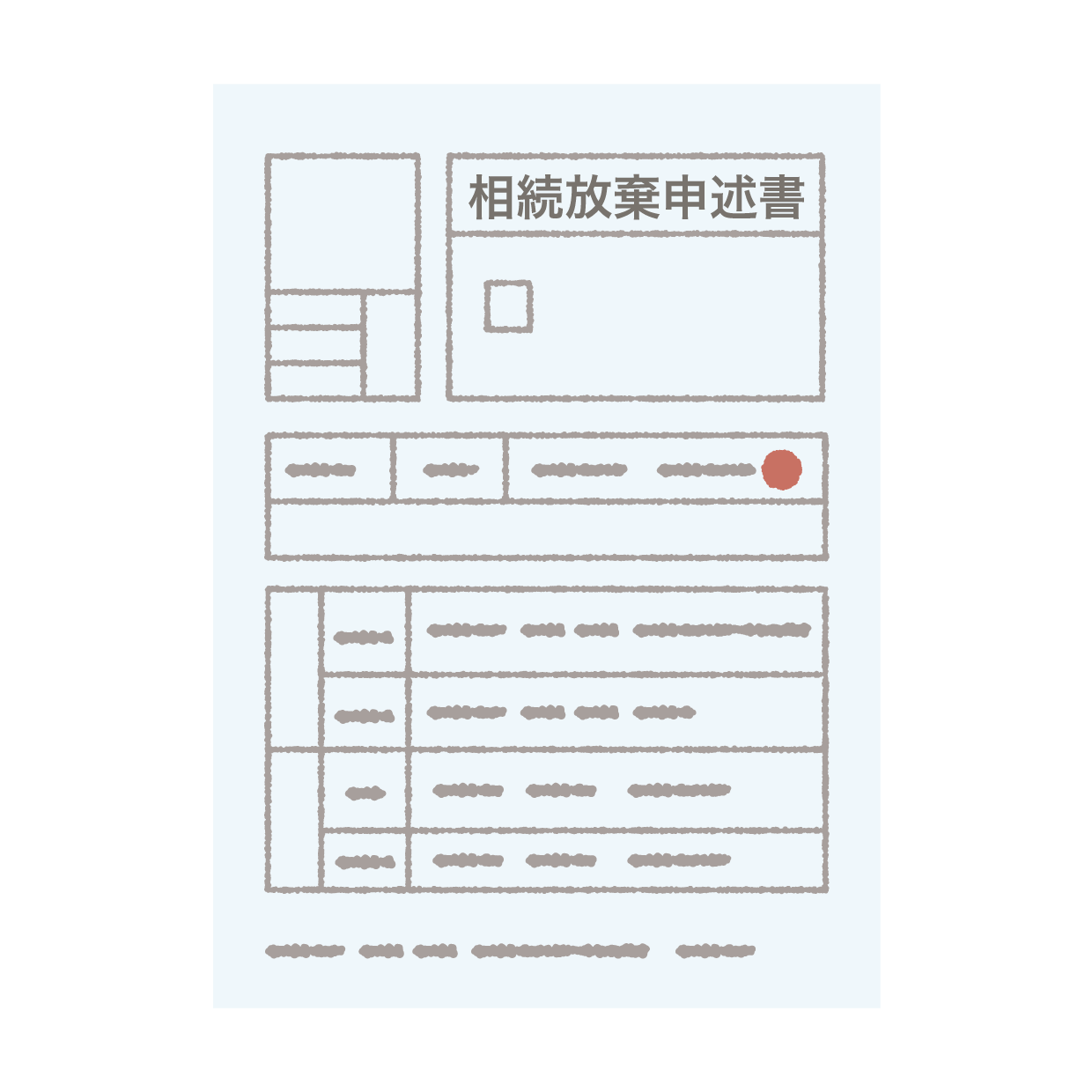
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しないこと、を指します。
遺産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産、有価証券など)とマイナスの財産(借金、負債、未払費用、保証債務など)の両方が含まれます。
相続放棄をすると、相続開始時から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を相続せずに済む点がメリットです。
逆に、預貯金などのプラスの財産を相続できなくなる点がデメリットとなります。
相続放棄の手続
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。
例えば、 被相続人の最後の住所が東京都の多摩地区であった場合、 東京家庭裁判所立川支部への申述が必要です。(東京都の家庭裁判所の管轄:https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/tokyo/index.html)
なお、申述の方法は、必ずしも裁判所の窓口に出向く必要はなく、郵送も可能です。
相続放棄の期限
相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、 行う必要があります(これを「熟慮期間」といいます)。
相続放棄の申述手続に要する必要書類は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍の附票、住民票除票といった役所で一度に取得できるものがほとんどです。
仮に、必要書類のすべてを3か月以内に用意できないおそれがあるとしても、相続放棄が認められる場合がありますので、あきらめず冷静に行動しましょう。
相続放棄をするか否かを3か月以内に決められない場合、「熟慮期間」を延長できる場合があります。延長の申請に必要な添付書類は基本的に相続放棄の申述と同じです。
相続放棄が受理されるまでの期間
家庭裁判所に申述書類を提出してから、家庭裁判所から申述受理通知書が発行されるまでの期間は、2週間から1か月程度であることが多いです。
相続放棄をする場合に注意すること
- 相続財産を「処分」してしまうと、 相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 相続放棄をした後であっても、相続財産を「隠匿」したり、私に「消費」したりした場合、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄をした後の管理義務
相続放棄をした後、相続人は遺産の管理義務を負う場合があります。また 当店 相続放棄は原則として 撤回することができません。相続放棄後も被相続人の財産に手をつけたり、勝手に処分したりすることは避けた方が良いです。
- 相続放棄をした場合でも、相続財産が残っていると、相続人は一定期間、その財産を管理しなければなりません。これは相続財産が放置されることによって 近隣住民に迷惑がかかったり、 財産の価値が毀損してしまうことを防ぐ目的です。例えば、空き家であれば倒壊しないように注意したり、雨漏りを修理したりするなどの対応が必要になる場合があります。
- ただし、相続財産清算人が選任されれば、その管理義務は「相続財産清算人」に移ります。
「相続財産清算人」とは
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)とは、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合など、相続財産の管理や清算業務を行う人がいない場合に、家庭裁判所によって選任される人を指します。清算後に残った財産は、最終的には国庫に帰属します。
相続財産を選任するためには、法定相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に対して選任の申し立てを行う必要があります。
「相続放棄」と「相続財産を受け取らないこと」との違い(よくある誤解)
相続放棄は、上記に説明したとおり、 一定の期限内に家庭裁判所への申述が必要になります。
これに対して、遺産分割を行う場面で遺産を全く取得せず、事実上相続財産を承継しなかったという行動をもって、相続放棄をしたと誤解なさる方がいらっしゃいます。しかし、この行動は正式な「相続放棄」に該当しません。そのため例えば相続財産の中に知人からの借入金が存在し、被相続人に代わって返済することを求められた場合、相続放棄を理由に返済を免れることはできない点に注意が必要です。
相続放棄とお墓
相続放棄をしても、お墓は継承できます。逆にいえば、もしお墓を継承したくない場合に相続放棄をしても継承を免れるわけではありません。お墓は「相続財産」ではないためです(「祭祀財産」という呼び方をします。)。
祭祀財産の継承問題については、基本的には相続財産とは別問題として取り扱うことになっています(実際には、相続人間で遺産分割で揉めている場合には祭祀継承の問題で揉めていることも多く、両者を同時に解決することもあります。)